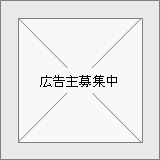MIDIをMP3に変換する方法
MIDIをMP3に変換する方法を紹介します。 ここではiTunesを使ってみます。Windowsで確認していますがMacでも大丈夫だと思いま... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
ギター用超小型チューナー「ミニヘッドストックチューナー PW-CT-12」
ギター用超小型チューナー「ミニヘッドストックチューナー PW-CT-12」の紹介です。 【国内正規品】 PlanetWaves プラネットウ... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
聴力を失った作曲家・佐村河内守氏の奇跡のシンフォニー「交響曲第1番 HIROSHIMA」
現代作曲家、佐村河内守氏の作品「交響曲第1番 HIROSHIMA」が収録されたCDの紹介です。 佐村河内守:交響曲第1番 HIROSHIMA... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
伊東福雄 楽しく学べる楽典準拠 クラシックギター音楽教本21
私のクラシックギターの師匠である伊東福雄氏が、このたびクラシックギター教本を出版する運びとなりましたので、そのご紹介です。 HM198 伊東... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
1秒間に66回!ギター速弾き世界記録がスゴい件
ギター速弾きの世界記録がYouTubeにアップされているのを発見しました。 下の動画はギタリストのTaylor Sterlingさんがアップ... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
定番のクリスマスソング一覧
どこかで一度は聞いたことがある、オーソドックスなクリスマスソング、あるいはクリスマスに演奏される作品の定番を集めてみました。 ここに掲載して... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
音楽コンクールで勝つ3つの方法
昨日、某クラシックギターコンクールのお手伝いに行ってきました。 ということで、音楽コンクールで勝つための3つの方法を、以前から感じていたこと... [記事ページへ]
Comments [3]
| Trackbacks [1]
音楽の基礎
音楽に携わっている方には必携の1冊です。 音楽の基礎 (岩波新書)芥川 也寸志 岩波書店 1971-08売り上げランキング : 1591お... [記事ページへ]
Comments [2]
| Trackbacks [0]
高品質な音楽を配信する音楽版 YouTube 「Blogmusik」
最近になって、Blogmusik という高品質な音楽を配信するサイトの存在を知りましたのでご紹介します。 久しぶりに音楽関係のエントリーです... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [9]
サンウェーブ CM 「パタパタくん」の変拍子を探る
TVで時々みかける、サンウェーブのCM「サンヴァリエ〈ピット〉」のテーマソングの拍子が以前から気になって仕方ありません。 サンヴァリエ〈ピッ... [記事ページへ]
Comments [3]
| Trackbacks [2]
天才クラシックギタリスト・山下和仁の超絶技巧「展覧会の絵」
YouTube に山下和仁「展覧会の絵」の演奏がありました。とりあえず聴いてみたい、という方は読み飛ばして、後方ある動画をご覧ください。 山... [記事ページへ]
Comments [4]
| Trackbacks [0]
日本生命CMのBGM「ニュー・シネマ・パラダイスのテーマ」の奏者を探る
最近バージョンが新しくなったようですが、日本生命CM・BGMのアコースティックな音色はいつ聴いても心が癒されます。 non data --... [記事ページへ]
Comments [2]
| Trackbacks [1]
ホルスト 組曲「惑星」 作品32(冥王星付き)
国際天文学連合の総会開催中、冥王星降格に反対するかのように、8月23日に発売されたCDです。 ホルスト:惑星(冥王星付き)ラトル(サイモン)... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [3]
ギターケース購入
先日、「アランフェス・ギターケース」というものを購入しました。 グラスファイバー製の軽量ケースで重さ3.9Kg。 街中でチェロのケースを肩に... [記事ページへ]
Comments [2]
| Trackbacks [0]
演奏会のお知らせ
音楽ネタで恐縮ですが、明日は私の所属するマンドリンアンサンブルのコンサートです。入場無料ですのでご都合がよろしければ是非お越しください。 明... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
村治佳織・右手急性疾患
日本を代表する女流クラシックギタリスト・村治佳織さんが右手急性疾患(右手後骨間神経麻痺:全治1ヶ月)を患ってしまったそうです。公式サイトでも... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [3]
資生堂フィティット・MAネールファイル
クラシックギターは爪を使って弾きます(使わない人もいます)。そして、この爪が弦にあたる角度や爪自体の仕上げ具合が音色に大きく関わってきます。... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [2]
コンクール採点用Excelシート
今日はギターコンクールのお手伝いに行ってました。このコンクールは各審査員(今年は10名)の採点した最高・最低得点を除く総合得点で競います。最... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
コンサートの個人的トピックス
コンサート無事終わりました。ご来場くださった方、ありがとうございました。 以下、個人的なトピックスです(音楽的な内容なし)。 スラックスの一... [記事ページへ]
Comments [4]
| Trackbacks [1]
A.ウルクズノフ・マスタークラス受講
27日、中目黒GTホールにてブルガリアのギタリスト兼作曲家、A.ウルクズノフのマスタークラスを受講してきました。 受講者はソロ3名・合奏1団... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
今年の音楽関係スケジュール
今日も行事が1日あり、とりあえずこれで年内のスケジュールは11月の演奏会だけだとホッとしていましたが、来週別のフェスティバルがあるのをすっか... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [1]
ギターコンクール
今日(23日)は某ギターコンクールのお手伝い(扉係)に行ってきました。今回は計41名の方が参加され、午前10:30から結果発表までの19:3... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [1]
ギターフェスティバル
本日は某ギターフェスティバルに参加します。 このフェスティバルでは個人的にひとつ大変なことがあります。演奏や運営に関してではありません。 実... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
次のコンサートは
9/5です。が昨日までそちらの曲に手をつける余裕がなかったので今日から暗譜開始。準備が遅いと言われるとみもふたもありませんが、はっきり言って... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
コンサート
本日ギターのコンサートありました。4人でソロ・二重奏・四重奏を弾くというプログラムですが私はリサイタルの半分くらいを弾いた印象。個人的には逼... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
「SUKIYAKI SONG」の由来
ご存知の通り、坂本九の大ヒット「上を向いて歩こう」のイギリスでのタイトルです。車に乗っている時、FMで作曲家・中村八大氏の特集をたまたま聞く... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [1]
「針のいらないレコードプレーヤー」考
株式会社エルプのレーザーターンテーブルはタイトル通り針の不要なレコードプレーヤー。針が不要なため原音に限りなく近い音質で楽しめるという点に加... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
演奏会当日の出来事
先日行われた演奏会での個人的なトピックス。演奏内容の感想はありません(笑)。 トゲ 舞台のセッティングで「山台」というオーケストラ後方の奏者... [記事ページへ]
Comments [3]
| Trackbacks [1]
アンサンブル・ビアンカフィオーリ演奏会
本日無事終了致しました。ご来場くださった方ありがとうございました。さすがに疲れましたので詳細は後日。... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
絵のような風景(その1)
今秋、所属しているマンドリンクラブでフランスの作曲家・J.マスネの作品「絵のような風景」の指揮をするのですが、参考用に管弦楽のCDを購入しま... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [1]
コンサートのお知らせ
アンサンブル・ビアンカ・フィオーリという社会人のマンドリンオーケストラに所属してまして、その定期演奏会が来週の土曜日開催されます。ということ... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
白い軌跡
クラシックギタリスト・河野智美さんがデビューソロアルバム「白い軌跡」およびチェロとのデュオ「10/100」をリリースされたので購入。 この方... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
アメイジング・グレイスはどこの民謡か
最近ではドラマ「白い巨塔」のエンディング等で使われていた美しい曲ですが、インターネットで調べてみると アメリカ民謡 イギリス民謡 スコットラ... [記事ページへ]
Comments [0]
| Trackbacks [0]
ピッチパイプ
フォークギターを弾き始めた中学生の頃、音叉の存在を知らなかった私は「ピッチパイプ(調子笛)」なるものを買って使ってました。ギター用のピッチパ... [記事ページへ]
Comments [2]
| Trackbacks [0]